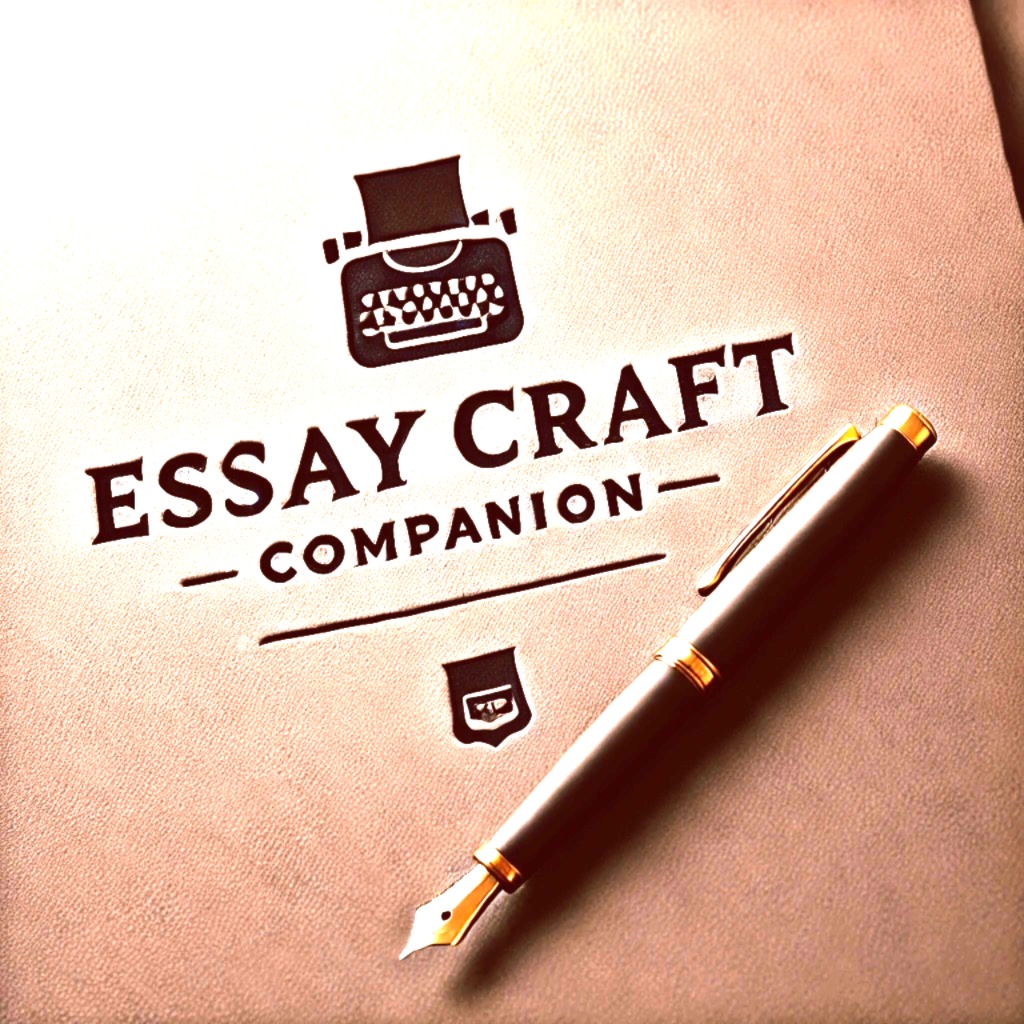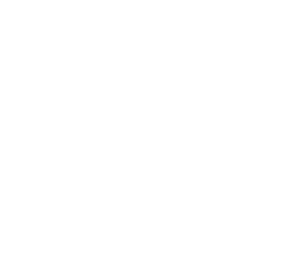「自由英作文」という表現の中に「自由」とあるが、決して「自由」ではない。自由なのは「表現する内容」だけで、バラバラと思ったことを書くわけではない。大切なのは、出題者の要求に答え、説得力を持って説明しきっているということである。
必要な作業は、抽出、配列、調整の三つのステップ。
抽出
① 要求を掘り起こす
作品を作り上げる際に、最低限盛り込む必要がある内容につながる要求や、語数制限などの、「内容」以外でも満たさなければならない形式的な要求を探す。

例えば、『「他人は自分のことをわかってくれない」と思うのはどんな時ですか。またそんなときに、あなたはどう対処しますか。また、それはなぜですか。70語程度の英語で説明しなさい。』という出題がある。どんな条件を満たすと、この問題に答えたことになるのだろうか? 「どんな時か」「その対処法」「なぜそれを選ぶのか」「70語程度の英語」という必要な要件を、問題文を見ながら挙げていく。
➁ 要求にできるだけ答える
要求を掘り起こすで出てきた要求に答える。「内容」につながる要求に答えることにより、作品に文章として盛り込む「内容」が決定されていく。この作業を上手にこなすと、「的確に答えている」という評価が得られる。また、形式的な要求は、この時点では基本的に答えられないので、作品を書き切った時に、一度立ち戻って確認をするように。
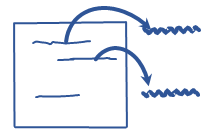
➂ 読み手の疑問を積極的に掘り起こして答える
「出題」と要求にできるだけ答える から出てきた「内容」の両方全部に目を通す。お話として全体を思い浮かべた時に、イメージの中で読み手が、あれ?っと思いそうな疑問や、説明が不十分だと感じそうな部分を見つけ出す。あらかじめその疑問に答え、その答えを「内容」に追加する。追加した状態で、再び全体を読みながら、最終的に読み手の疑問がなくなるまでこの作業を繰り返す。この作業を上手に完遂すると、「説得力がある」という評価につながる。
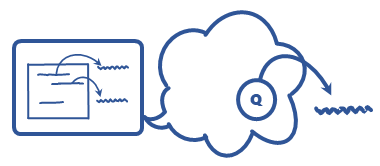
この読み手の疑問を見つけ出すのは、本当に難しい。ある程度高等教育を受けた一般の読者を想定し、その読者が「どういうこと?」「なんで?」「ふつうある?」「誰と?」などと、疑問に思う確率が高そうなものを頭の中で見つけ出す。そして、その答えに当たる部分を、文章として表し、それを本文全体の一部に組み込むと、「説明がきちんとなされている」という状態が担保され、読み手のフラストレーションを軽減することができる。この状態を目指すために、頭をフル回転!
配列
抽出を経て、紡ぎ出した「内容」で表される文章を材料としながら、どの文章から始め、どの文章につないでいくと、最終的にすべての「内容」を含むお話しとして成立させることができるのかを悩みながら、作品の構成を考える。
細かい部分で言うと、スムーズに話しを進めるために、紡ぎだした文章の途中や前後に小さく表現を付け足す場合もあるし、新たに一文をまるまる加える場合もある。また、全体として、どの文章から、どの文章につなげて、どの文章で終わらせると、スムーズにつながるのかを考えながら、構成していく。全体の流れを決める力と、文と文を丁寧につなげる力をバランスよく発揮させる。
例えば、「写真を描写する」という出題に遭遇したとする。まずは、そもそも普段どうしているかを考えてみましょう。いろんな説明の仕方があると思いますが、その中でも、例えば、おおまかに何の写真なのかを言い、その後に、それを撮った経緯、そこでのお話を、写真の中にある小道具である小さな部分を織り交ぜながら、相手に伝えられる、などと気が付いたら、それを、その順で英語にしていきます。では、相手から、悩み事を打ち明けられた場合は、どうしたらいいでしょう。これも人によるとは思いますが、すぐさま答えを言わずに、理解、同情を示し、その後に、どうしていったらいいかのアドバイスをする人が多いと思います。それに気づけば、その流れに従って、作品を作り上げていきます。こうやって考えると、具体的に対策をとっていなかった問題にだけではなく、「新しい傾向」と称される問題にも対処できるようになります。どんなものにでも、対応できるあなたが出来上がりますように!
調整
抽出、配列を通して出来上がった全体を眺め、違和感のある部分を直したり、きちんと出題に答えられたかの最終確認をする。
➀ 滑らかにする
「内容」を抽出したときに全体像が見えにくかったり、英文にするときに表現しやすいものを選択したなどのせいで、配列すると読み手に誤解させる可能性がある部分が生じることがある。出来上がった全体を眺め、その誤解させそうな部分を察知し、直す。
② 整える
最終的に出題に答えたかを確認する。語数調整に取り組んだり、「自分の考えを述べなさい」などの要求を実現できているかの確認をしたりする。